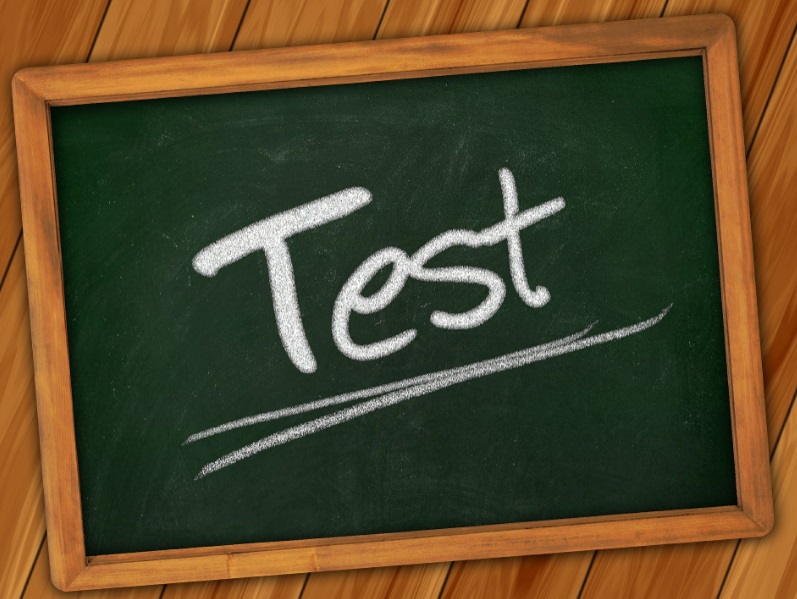サブロー
【危険物乙4】受験者必読 !!『危険物取扱者試験 乙4 』の資格取得を最終的な目的とし、試験に出そうな内容をピックアップして出題します。丸暗記するくらい解いていきましょう!!!
Question.41:次の記述の中で誤っているものはどれか選べ。
分類:法令 申請・届け出
1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。
2. 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。
3. 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される貯蔵所を設置しようとする者は、貯蔵所ごとに、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 1つの区域のみに移送取扱所を設置しようとする者は、当該市町村長の許可を受けなければならない。
5. 取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事または総務大臣は、変更許可の申請があった場合において、その取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、取扱所においておこなう危険物の取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.41:1
【解説・補足】
1. (✖) 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。 ⇨ 『市町村長に届出』ではなく、『市町村長の許可』を受ける必要がある。
2. (〇) 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。 ⇨ 問題分の通り。例外があることは覚えておこう!!
3. (〇) 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される貯蔵所を設置しようとする者は、貯蔵所ごとに、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。⇨ 問題分の通り
4. (〇) 1つの区域のみに移送取扱所を設置しようとする者は、当該市町村長の許可を受けなければならない。⇨ 問題分の通り
5. (〇) 取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事または総務大臣は、変更許可の申請があった場合において、その取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、取扱所においておこなう危険物の取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。 ⇨ 問題分の通り
参考講座☞☞☞【スキルアップ-危険物乙4】『危険物を取り扱うための申請・届出』_第32回
Question.42:次の記述の中で誤っているものはどれか選べ。
分類:法令 危険物に関する法令
1. 製造所、貯蔵所または取扱所を設置しようとする者は、行政庁の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更しようとする者も、同様とする。
2. 製造所、貯蔵所または取扱所の設置(変更)許可申請を受けた市町村長等は、技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所または取扱所における危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
3. 総務大臣は、2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所について許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事および関係市町村長は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
4. 設置(変更)許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置(変更)したとき、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。
5. 製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は設置(変更)許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、設置(変更)許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.42:4
【解説・補足】
1. (〇) 製造所、貯蔵所または取扱所を設置しようとする者は、行政庁の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更しようとする者も、同様とする。 ⇨ 問題分の通り
2. (〇) 製造所、貯蔵所または取扱所の設置(変更)許可申請を受けた市町村長等は、技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所または取扱所における危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。 ⇨ 問題分の通り
3. (〇) 総務大臣は、2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所について許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事および関係市町村長は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 ⇨ 問題分の通り
4. (✖) 設置(変更)許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置(変更)したとき、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。 ⇨ 問題文の通りだが、但し書きとして「ただし、製造所等の設備などを変更する場合に、変更工事に係る部分以外の全部または一部を市町村長の承認を得て完成検査前に使用することができる。」と続き、変更工事以外の部分は使用できる『仮使用』に関してが抜けているため間違いとなる。
5. (〇) 製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は設置(変更)許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、設置(変更)許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 ⇨ 問題分の通り
仮使用:市町村長等の承認を受けて、変更工事以外の部分を仮に使用すること。
参考講座☞☞☞【スキルアップ-危険物乙4】『危険物を取り扱うための申請・届出』_第32回
Question.43:次の記述の中で誤っているものはどれか選べ。
分類:危険物の指定数量
1. いかなる時であっても、指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。
2. 製造所、貯蔵所または取扱所において、危険物の貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従わなければならない。
3. 指定数量の0.2未満の危険物については規制されていない。
4. 製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
5. 指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、市町村条例で定める。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.43:1
【解説・補足】
1. (✖) いかなる時であっても、指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 ⇨但し書きがあり、『ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。』とあり、所轄消防長または消防署長の承認を受けた場合は取り扱える。
⇨【仮貯蔵】と呼ぶ。
2. (〇) 製造所、貯蔵所または取扱所において、危険物の貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従わなければならない。 ⇨ 問題分の通り
3. (〇) 指定数量の0.2未満の危険物については規制されていない。 ⇨ 問題分の通り
4. (〇) 製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 ⇨ 問題分の通り
5. (〇) 指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、市町村条例で定める。 ⇨ 問題分の通り
参考講座☞☞☞ 【スキルアップ-危険物乙4】『危険物の指定数量』_第8回
Question.44:次の記述の中で正しいものはどれか選べ。
分類:法令 危険物取扱者
1. 丙種危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の危険物の取扱いに立ち会うことができる。
2. 丙種危険物取扱者は、すべての第四類の危険物を取り扱える。
3. 丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になれる。
4. 乙種4類の危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の第四類の危険物の取扱いに立ち会うことができる。
5. 乙種4類の危険物取扱者は、危険物第1類を取り扱える。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.44:4
【解説・補足】
1. (✖) 丙種危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の危険物の取扱いに立ち会うことができる。 ⇨ 無資格者が危険物を取り扱うときの立会いはできない。
2. (✖) 丙種危険物取扱者は、すべての第4類の危険物を取り扱える。 ⇨丙種危険物取扱者が取り扱える危険物は、第4類の危険物のうち、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類、第4石油類、動植物油類に限定される。
3. (✖) 丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になれる。 ⇨保安監督者になれるのは甲種危険物取扱者と乙種危険物取扱者(免状に指定された類のみ)
4. (〇) 乙種4類の危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の第4類の危険物の取扱いに立ち会うことができる。 ⇨ 問題分の通り
5. (✖) 乙種4類の危険物取扱者は、危険物第1類を取り扱える。 ⇨乙種4類の危険物取扱者は第4類の危険物のみしか取扱いできない。
参考講座☞☞☞ 【スキルアップ-危険物乙4】『危険物取扱者とは』_第2回
Question.45:次の記述の中で誤っているものはどれか選べ。
分類:性質 第4類の危険物
1. 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で、引火点が21℃未満のものをいう。
2. 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。
3. 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧で、引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
4. 動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が200度未満のものをいう。
5. 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいう。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.45:4
【解説・補足】
1. (〇) 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で、引火点が21℃未満のものをいう。 ⇨ 問題分の通り
2. (〇) 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 ⇨ 問題分の通り
3. (〇) 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧で、引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。 ⇨ 問題分の通り
4. (✖) 動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が200度未満のものをいう。 ⇨ 「200℃未満」の表記が誤り。動植物油類とは、1気圧において引火点が250℃未満のものである。
5. (〇) 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいう。 ⇨ 問題分の通り
参考講座☞☞☞ 【スキルアップ-危険物乙4】『危険物の性質の概要②』_第10回

モグゾー
それでは、今回はここまで。最後までお読みいただきありがとうございました!
下の模擬試験も是非ご覧下さい!!
2020年10月18日公開 | 2020年11月24日更新