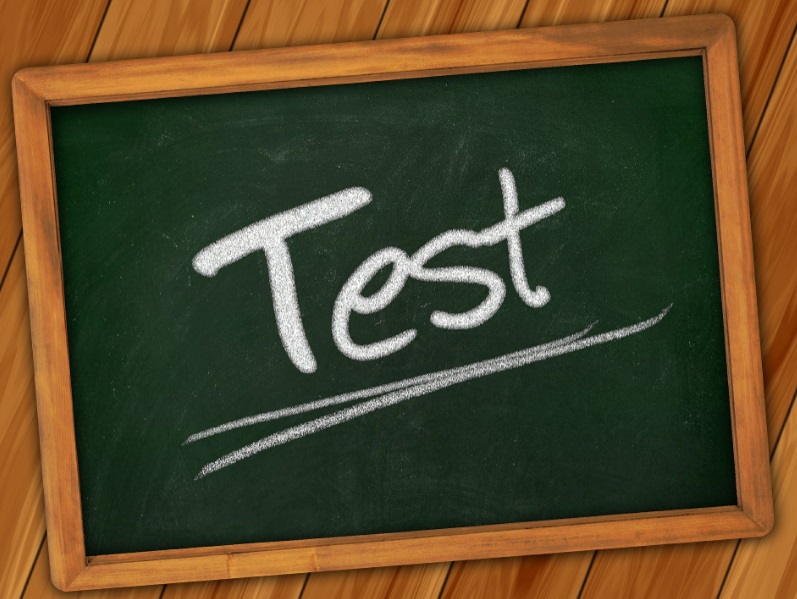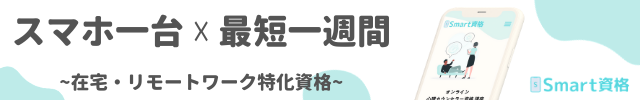サブロー
【危険物乙4】受験者必読 !!『危険物取扱者試験 乙4 』の資格取得を最終的な目的とし、試験に出そうな内容をピックアップして出題します。丸暗記するくらい解いていきましょう!!!
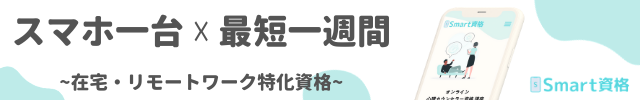

Question.11:第4類の危険物の貯蔵・取扱いにおいて、次のうち間違っているものはどれか?
分類:危険物の性質-第4類の危険物に共通する特性
1. 直射日光を避けて、冷所に貯蔵すること。
2. みだりに蒸気を発生させないこと。
3. 加熱は避けること。
4. 炎や火花等との発火の原因となる高温体との接近は避けること。
5. 寒冷地では液温の低下を避けること。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.11:5
【解説・補足】
1. (〇) 直射日光を避けて、冷所に貯蔵すること。 ⇨ 密栓して貯蔵が基本。膨張を防ぐ為に容器中に空間を作ることも重要
2. (〇) みだりに蒸気を発生させないこと。
3. (〇) 加熱は避けること。
4. (〇) 炎や火花等との発火の原因となる高温体との接近は避けること。
5. (✖) 寒冷地では液温の低下を避けること。 ⇨ 特に貯蔵として注意すべき点とはされていません。
参考講座☞☞☞ 【危険物の性質の概要②】-【危険物乙4】資格取得#10
Question.12:一般取扱所について誤っているものはどれか?
分類:危険物の法令-一般取扱所の基準
1. 天井を有してはいけない。
2. アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等、ヒドロキシルアミン等を取扱う一般取扱所には、基準を超える特例が定められる。
3. 一般取扱所とは、指定数量以上の危険物を取扱う施設で、他の取扱所に分類されないすべての取扱所である。
4. 保有空地はない。
5. 高引火点危険物のみを取扱う一般取扱所については、基準の特例を定めることができる。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.12:4
【解説・補足】
1. (〇) 天井を有してはいけない。
2. (〇) アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等、ヒドロキシルアミン等を取扱う一般取扱所には、基準を超える特例が定められる。
3. (〇) 一般取扱所とは、指定数量以上の危険物を取扱う施設で、他の取扱所に分類されないすべての取扱所である。
4. (✖) 保有空地はない。 ⇨ 保有空地とは、危険物を取り扱う施設の周囲に、消火活動や延焼防止のために設けられた空地のことであり、どのようなものを置くことができません。保有空地が不要なのは、『屋内タンク貯蔵所』『地下タンク貯蔵所』『移動タンク貯蔵所』『給油取扱所』『販売取扱所』の5つです。
5. (〇) 高引火点危険物のみを取扱う一般取扱所については、基準の特例を定めることができる。
参考講座☞☞☞ ~Coming soon!!~
Question.13:電気火災において用いることができる消火剤として、適切なものを選べ。
分類:危険物の物理・化学-消火方法
1. 機械泡で放射する消火器。
2. 棒状の水を放射する消火器。
3. 二酸化炭素を放射する消火器。
4. 強化液を棒状に放射する消火器。
5. 泡を放射する消火器。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.13:3
【解説・補足】
1. (✖) 機械泡で放射する消火器。 ⇨ 水系消火器で、感電する恐れがあるので使用しません。
2. (✖) 棒状の水を放射する消火器。 ⇨ 棒状の水を放射する消火器は、感電する恐れがあるので、使用しません。但し、霧状放射であれば電気火災に有効である。
3. (〇) 二酸化炭素を放射する消火器。 ⇨ 酸素濃度を低下させる窒息効果がある。他にはハロゲン化物消化器、粉末消火器も有効である。
4. (✖) 強化液を棒状に放射する消火器。 ⇨ 強化液を棒状に放射する消火器は、感電する恐れがあるので使用しません。但し、霧状放射であれば電気火災に有効である。
5. (✖) 泡を放射する消火器。 ⇨ 水系消火器で、感電する恐れがあるので使用しません。
参考講座☞☞☞ 【燃焼と消火】の要素-【危険物乙4】資格取得 #15
Question.14:予防規定に定める必要がないものは、次のうちどれか?
分類:危険物の法令-予防規定
1. 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及びその組織に関すること。
2. 危険物の保安に関わる作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
3. 消火設備、警報設備、避難設備の整備に関すること。
4. 危険物の取扱い作業の基準に関すること
5. 危険物保安監督者が、旅行、疾病、その他の自己によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.14:3
【解説・補足】
1. (〇) 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及びその組織に関すること。
2. (〇) 危険物の保安に関わる作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
3. (✖) 消火設備、警報設備、避難設備の整備に関すること。 ⇨ 定める必要はありません。
4. (〇) 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
5. (〇) 危険物保安監督者が、旅行、疾病、その他の自己によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
⇨職務代行者のこと
参考講座☞☞☞ 【予防規定】-【危険物乙4】資格取得 #17
Question.15:消火設備について誤っているものはどれか?
分類:危険物の法令-消火設備
1. 第5種の消火設備は、原則として防護対象物から消火設備までの歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。
2. 地下タンク貯蔵所は、第5種の消火設備を2個以上設けること。
3. 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
4. 移動タンク貯蔵所は、自動車用消火器等を2個以上設けること。
5. 第4種の消火設備は、原則として防護対象物から消火設備までの歩行距離が40メートル以下となるように設けなければならない。
+正解は・・・・・(クリックして下さい)
Answer.15:5
【解説・補足】
1. (〇) 第5種の消火設備(※)は、原則として防護対象物から消火設備までの歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。
※第5種消火設備:小型消火器、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩
2. (〇) 地下タンク貯蔵所は、第5種の消火設備を2個以上設けること。
3. (〇) 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100平方メートルごとに1個以上設けるものとする。
4. (〇) 移動タンク貯蔵所は、自動車用消火器等を2個以上設けること。
5. (✖) 第4種の消火設備は、原則として防護対象物から消火設備までの歩行距離が40メートル30メートル以下となるように設けなければならない。
参考講座☞☞☞ Coming Soon!!

モグゾー
それでは、今回はここまで。最後までお読みいただきありがとうございました!
下の模擬試験も是非ご覧下さい!!
2020年9月25日公開 | 2020年10月9日更新