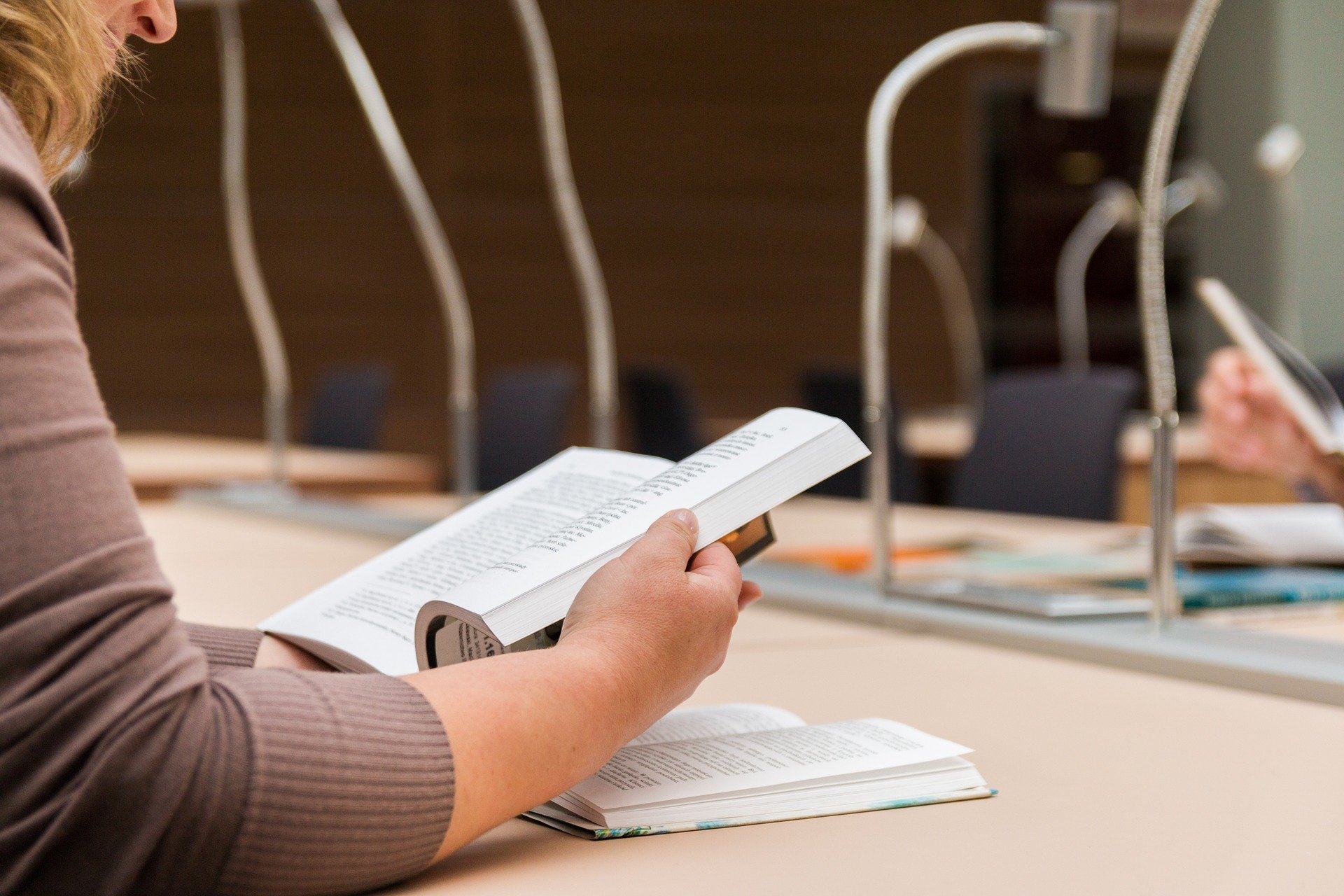【~~随時更新中~~】

今回の対策講座の今回は、
分類:『物理・科学』
の項目で重要な部分のみを抜粋して説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
目次
暗記項目
〇水の密度は4℃の時が最大である。そのときの体積は最小である。
〇引火点とは、その温度以上で火を近づけると燃える温度。
〇燃焼範囲とは、その範囲の濃度であれば火を近づけると燃える濃度。
〇同素体とは、同じ原子で出来ている単体でありながら、科学的性質が異なるもの同士のこと。
⇨S-硫黄、C-炭素、O-酸素、P-リン の4つで SCOP(スコップ)を覚えておけばいい。
〇同位体とは、原子番号が同じで、質量数の異なる原子同士のこと。例:水素と重水素
〇異性体とは、同じ種類の原子を持っているが、違う構造をしている物質のこと。例:キシレン(3つの異性体有り)
法則
① 質量保存の法則 ⇨ 化学変化の前後では、物質全体の質量の総和は変化しない。
② 倍数比例の法則 ⇨ 異なる2種の元素からなる化合物では、一方の元素の一定質量と化合する他の元素の質量は、簡単な整数比となる。
③ 定比例の法則 ⇨ 同じ化合物であれば、化合物を構成する元素の質量比は常に一定である。
④ アボガドロの法則 ⇨ すべての気体1molは、標準状態で22.4リットル、気体分子数は6.02×1023個。
物質の状態変化
〇固体、液体、気体間の状態変化時には温度は変化しない。

①液化(凝縮):気体が液体になる。(熱を放出)
②気化(蒸発):液体が気体になる。(熱を吸収)
③融解:固体が液体になる。(熱を吸収)
④凝固:液体が固体になる。(熱を放出)
⑤昇華:固体が気体になる、また気体が固体になる。(熱を吸収、熱を放出)
メモ
水の蒸発熱(気化熱)は2263.8J/g(100度、539cal/g)と大きく、また熱容量も大で、冷却効果が大きく、また水蒸気になると体積が約1700倍に膨張して窒息効果があることなどにより、水は有効な消化剤として使われている。
沸騰と沸点
〇沸点とは、液体の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる液温のことである。
・外圧が高くなれば、沸点も高くなる。
・外圧が低くなれば、沸点も低くなる。
メモ
水に塩などの不揮発性物質を溶かすと、水溶液の沸点は高くなり、凝固点は下がる。
潮解と風解
〇潮解:個体が空気中の水分を吸収して溶けること。
〇風解:個体に含まれる水分が失われて粉末になること。
酸と塩基
〇酸:水に溶けると電離して水素イオン(H+)を生じる物質、または他の物質に水素イオンを与える物質のこと。酸性。
例:HCL→H++CL-
〇塩基:水に溶けると電離して水酸化物イオン(OH-)を生じる物質、または他の物質に水素イオンを受け取る物質のこと。塩基性。
例:NaOH→Na++OH-
〇中和:酸と塩基を混合した際に、塩(えん)と水を生成する反応のこと。(=中和反応)
〇リトマス紙:酸は青色リトマス紙を赤に変え、塩基は赤色リトマス紙を青色に変える。
〇pH値(水素イオン指数):中性は"7"、値が小さければ酸性を示し、値が大きければ塩基性を示す。
酸化と還元
〇酸化:酸素と化合したり、水素を奪われたり、電子を失ったりすること。
例1:鉄が空気中に放置しておくと赤くさびて酸化鉄ができる。
例2:銅を熱すると表面に酸化膜ができる。
例3:一酸化炭素が完全燃焼して酸素と結びつくと二酸化炭素ができる。
酸化剤:他の物質を酸化させる目的で使用するもので、水素を奪う性質のあるもの。酸化剤自身は還元される。
〇還元:酸素を奪われたり、水素と化合したり、電子を受け取ったりすること。
例1:酸化銅は炭素により酸素が失われて銅になる。
還元剤:他の物質を還元させる目的で使用するもので、水素を与える性質のあるもの。還元剤自身は参加される
メモ
酸化と還元は必ず同時に起こる(=酸化還元反応)
ボイル・シャルルの法則
〇ボイルの法則:温度が一定の状態では、気体の体積(V)は圧力(P)に反比例する。
P1V1=P2V2
(圧力P1、体積V1を圧力P2、体積V2にした場合の関係式)
〇シャルルの法則:圧力が一定の状態では、一定質量の体積(V)は温度(T)に比例する。
V2=V1×T2/T1
(絶対温度T1、体積V1の気体を、絶対温度T2、体積V2にした場合の関係式)
〇ボイルシャルルの法則:一定質量の気体の体積は、圧力に反比例し、絶対温度に比例する。
P1×V1/T1=P2×V2/T2
(絶対温度T1・圧力P1・体積V1気体を、絶対温度T2・圧力P2・体積V2にした場合の関係式)
メモ
絶対温度:摂氏-273℃を0℃とするもので、単位はK(ケルビン)。0K⇨原子や分子の動きが停止する温度
熱
〇熱容量:物体の温度を1℃(1K)上げるのに必要な熱量のこと。単位はJ/℃ またはJ/K
熱容量=比熱×質量 ➩ Q(J)=c×m
〇熱量:熱エネルギーの大きさを表す量で単位はJ(ジュール)。物体を熱したり、冷やしたりするときに物体に出入りする熱の量のこと。
熱量=熱容量×温度変化=比熱×質量×温度変化 ➩ Q(J)=C×(t2-t1)=c×m×(t2-t1)
〇比熱:物質1gの温度を1℃(1K)上げるために必要な熱量のこと。単位はJ/(g・℃) またはJ/(g・K)
例:比熱が2.8(j/g・℃)である液体200gが20℃から30℃まで上昇させるのに必要な熱量は?
Q=2.8(J/g・℃)×200g×10℃=5600J(5.6kJ)
〇熱の移動
★熱は高温物体から低温物体へ移動する。移動の方法は下記。
・伝導:熱が物質の中を伝わっていく現象
・対流:温度差によって液体や気体が移動して熱が運ばれる現象
・放射(ふく射):高温の物体から出る光としての熱エネルギーを吸収して、熱エネルギーのあたる部分の温度が上がる現象
〇熱伝導率:固体>液体>気体 金属>非金属
・熱伝導率が大きい=熱が伝わりやすい=熱の移動が早いので蓄積しにくい=物質の温度は上がりにくい。
・熱伝統率が小さい=熱が伝わりにい=熱の移動しにくいので蓄積しやすい=物質の温度は上がりやすい。
〇熱膨張:温度の上昇につれて長さや体積が増加すること。
長さ:線膨張
体積:体膨張 (体膨張率:気体>液体>固体)
体積V0の物質がt℃上昇したときの体積Vは V=V0×(1+α×t) 膨張後の体積=元の体積×(1+体膨張率×温度変化)
例:1000ℓのある液体が10℃から30℃まで上昇したとき、体積は何リットル増加するか?体膨張率は1.35×10-3K-1とする。
V=1000×(1+1.35×10-3×20)=1027ℓ 1027-1000=27ℓ 答え:27ℓ
燃焼
蒸発燃焼:可燃性蒸気が燃焼する。液体の燃焼は、すべてこの「蒸発燃焼」です。液体が燃えるのではなく、蒸発した可燃性蒸気が燃焼する。固体の場合、液体にならずに固体からそのまま気体になる。例:硫黄、ナフタレン、赤リン、マグネシウム
分解燃焼:可燃性固体が熱によって分解を起こし、可燃性蒸気が発生して燃焼する。また分解燃焼のうち、酸素を含む物質の燃焼を内部燃焼(自己燃焼)をいう。例:紙、木材、石炭、ニトロセルロース、
表面燃焼:可燃性固体が酸化反応して、固体の表面から内部へと燃焼する。例:木炭、コークス
定常燃焼:バーナー燃焼。炎の位置や形状を制御できる。
・予混合燃焼:空気を混合させた可燃性気体を噴出する燃焼
・非予混合燃焼:可燃性気体を噴出するときに空気と混合気体になる燃焼
非定常燃焼:爆発燃焼.。可燃性ガスと空気の混合気体に点火し爆発的に拡大し制御不能な燃焼のこと。例:エンジン内のガソリンの燃焼
静電気
〇電気的に絶縁された2つの異なる物質が接触すると、一方が正(+)、他方が負(-)の電化を帯びることにより発生する。
〇電気の不導体(絶縁体)を摩擦すると静電気が発生する。
〇静電気が蓄積すると、放電火花が発生し、これが点火源になることがある。
〇一般に液体や粉体が流動すると、流動摩擦等により静電気が発生しやすい。
〇帯電には、接触帯電、流動帯電、噴出帯電がある。
〇静電気防止
・導電性材料を用いる。
・アース(接地)する。
・加水・加湿(75%以上)する。
・帯電防止剤を添加する。
・空気をイオン化し、電気伝導率を大きくする。
・接触、剥離回数を減らす。
・接触面積を小さくする。
・接触圧力を低くする。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
関連
危険物乙4 の講義内容(法令編)
【スキルアップ-危険物乙4】『試験に出るポイントのまとめ』_法令編
関連
危険物乙4 の講義内容(性質・消火編)