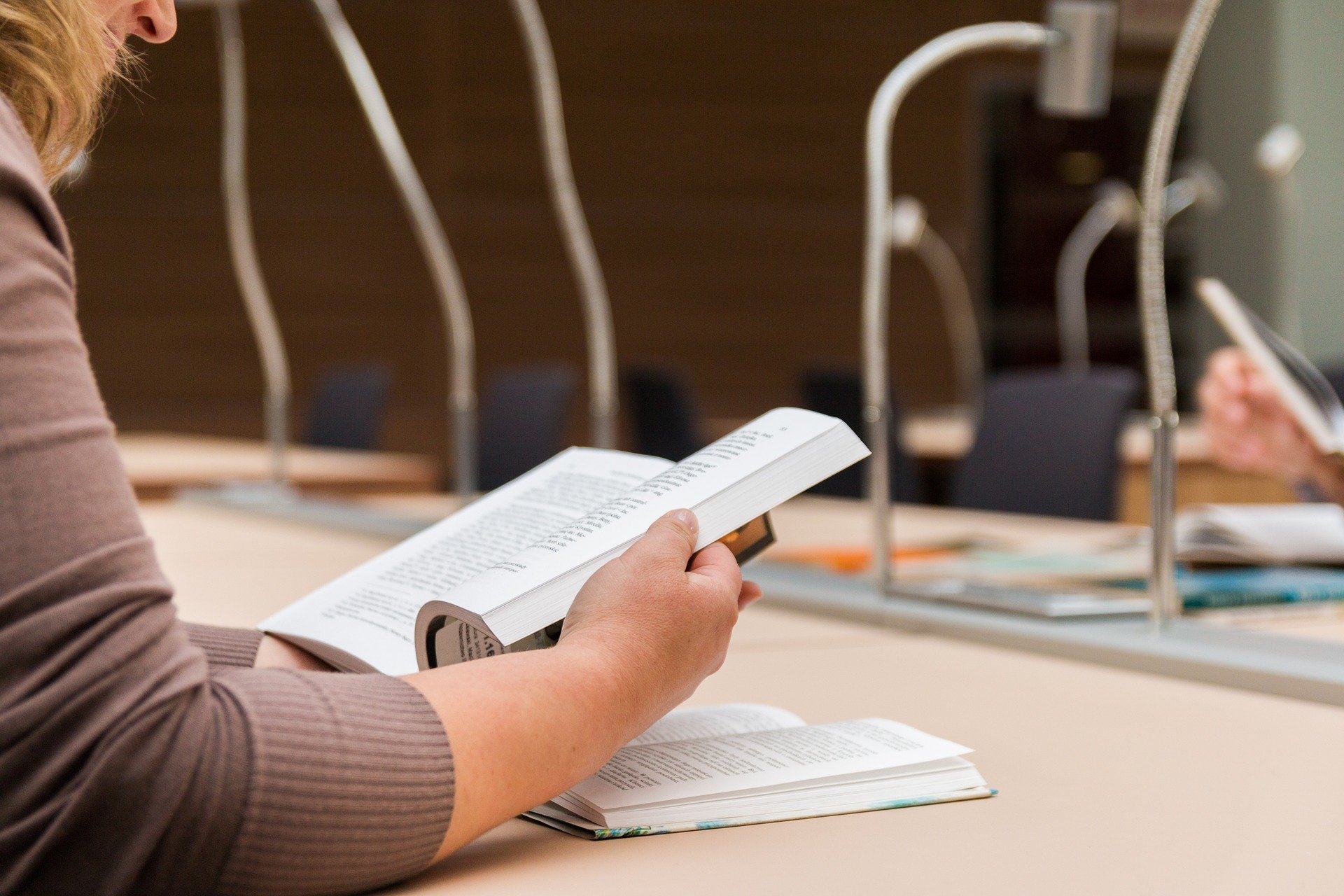【~~随時更新中~~】

今回の対策講座の今回は、
分類:『法令』
の項目で重要な部分のみを抜粋して説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
目次
法令上の危険物
消防法によって法律の品名欄に掲げる物品で、性質によって第1~第6類に区分される。
〇第1類:酸化性固体・・・不燃性固体、酸素を含み、他の物質を酸化させる。
〇第2類:可燃性固体・・・可燃性固体、還元性、低温で着火、引火しやすい。
〇第3類:自然発火性物質、禁水性物質・・・液体または固体、可燃性(一部不燃性)
〇第4類:引火性液体・・・液体、可燃性、還元性
〇第5類:自己反応性物質・・・液体または固体、可燃性、酸素を含み、加熱・摩擦・衝撃などで分解し、自己燃焼を起こす。
〇第6類:酸化性液体・・・液体、不燃性、酸素を含み、他の物質を酸化させる。
※危険物は1気圧20℃において、液体か固体であり、水素やプロパンガスのような気体は消防法では危険物ではない。

〇酸化性:加熱や衝撃で酸素を放出し、他の物質の燃焼を助ける。↔還元性:酸化されやすい(酸素と反応しやすい)
〇燃焼性:燃焼する=可燃性、燃焼しない=不燃性
〇引火性:火や熱などの点火源によって、可燃性のものが発火する物質
〇自己反応性:自分自身で燃焼する性質。酸素を含んでいる。
申請・届け出
★届け出
〇危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更⇨⇨⇨変更しようとする日の10日前までに届け出(市町村長等へ)
〇製造所の譲渡・引き渡し⇨⇨⇨遅延なく届け出(市町村長等へ)
〇製造所等の廃止⇨⇨⇨遅延なく届け出(市町村長等へ)
★届け出先
〇都道府県知事:免状の交付・書換・再交付。製造所等が行う手続きで、設置場所の市町村に消防本部・消防署を置いていない場合
〇消防署長:仮貯蔵の承認
〇市町村等:その他全部
〇総務大臣:移送取扱所が行う手続きで、設置場所が2つ以上の都道府県の区域にまたがって設置する場合
★申請の種類
〇許可:製造所等の設置・変更
〇検査:完成検査前検査(※)、完成検査
〇承認:仮貯蔵・仮取り扱い・仮使用
〇認可:予防規定の制定・変更
※完成検査前検査は液体危険物タンクを有する場合に完成検査前に受ける検査のこと。
メモ
仮貯蔵とは?
消防長又は消防署長の承認を得て指定数量以上の危険物を10日以内で仮に貯蔵または取扱うこと。
メモ
仮使用とは?
製造所等の位置、構造、設備を変更する場合、工事中に工事に係る部分以外の一部または全部を市町村長の承認を受けて完成検査前に使用すること。
危険物取扱者
〇危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事より免状を交付されたもの。10年間有効
〇免状の種類:
・甲:第1~第6類 すべての危険物の取扱が可能
・乙:免状に記載された危険物の取扱が可能
・丙:第4類の危険物のうち、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類の一部、第4石油類、動植物油の取り扱いが可能
〇免状の交付:都道府県知事に申請
〇免状の書換:氏名、本籍地、免状の写真が10年経過→→交付した知事、居住地もしくは勤務地を管轄する知事
※住所変更では書換は不要である。
〇免状の再交付:紛失、破損等→→交付した知事、または書換を行った知事
※汚損・破損の場合は、その免状を添えて申請。紛失したものが見つかった場合は、再交付を受けた都道府県知事に10日以内に提出
危険物保安監督者
〇資格:甲種、または乙種の危険物取扱者で製造所等において6か月以上の実務経験を要する。(丙種は不可!!)
〇選任・解任:市町村長等に遅延なく届ける。
〇危険物施設保安員がいる場合は必要な指示を行い、いない場合は危険物施設保安員の業務を行う。
〇必要な製造所等
・製造所
・屋外タンク貯蔵所
・給油取扱所 (語呂合わせ用:ガソリン)
・移送取扱所 (語呂合わせ用:パイプライン)
・一般取扱所 (語呂合わせ用:ボイラー)
語呂合わせ
製造所の監督は横文字のオク買いタンク
製造所(せいぞうしょ)・危険物保安監督者(かんとくしゃ)・横文字(ガソリン/パイプライン/ボイラー)・屋外タンク(オク買いタンク)貯蔵所
危険物保安統括責任者
〇大量の第4類の危険物を取扱う事業者においては、事業全体の保安業務を統括管理する危険物保安統括管理者が必要である。
〇特に必要な資格はない。
〇選任・解任した場合は、市町村長等に遅延なく届ける。
〇選任が必要な事業所
・指定数量の倍数が3000以上の製造所と一般取扱所
・指定数量以上の移送取扱所
第4類の種類
危険性が高い順番
★特殊引火物:1気圧において、発火点が100℃以下、引火点が-20℃以下、沸点が40℃以下
★第1石油類:1気圧において、引火点が21℃未満
★アルコール類:1分子を構成する炭素の原子が1~3個までの飽和1価アルコール(含有量60%未満の水溶液は除く)
★第2石油類:1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満
★第3石油類:1気圧において、引火点が70℃以上200℃未満
★第4石油類:1気圧において、引火点が200℃以上250℃未満
★動植物油類:1気圧において、引火点が250℃未満の動物の脂肉、植物の種子等から抽出したもの
第4類の危険等級
危険物の危険性に応じての区分で、Ⅰが危険度大となる。
〇危険等級Ⅰ:特殊引火物
〇危険等級Ⅱ:第1石油類、アルコール類
〇危険等級Ⅲ:特殊引火物、第1石油類、アルコール類以外の第4類危険物
指定数量
メモ
指定数量は?
危険性の基準になる数量で、「危険物の規制に関する政令(別表)」で定められた数値。
・指定数量以上の貯蔵・取扱い⇨⇨⇨消防法の規制
・指定数量未満の貯蔵・取扱い⇨⇨⇨市町村条例の規制
| 品名 | 水溶性 | 指定数量 |
| 特殊引火物 | 非水溶性 | 50ℓ |
| 水溶性 | ||
| 第1石油類 | 非水溶性 | 200ℓ |
| 水溶性 | 400ℓ | |
| アルコール類 | 水溶性 | 400ℓ |
| 第2石油類 | 非水溶性 | 1000ℓ |
| 水溶性 | 2000ℓ | |
| 第3石油類 | 非水溶性 | 2000ℓ |
| 水溶性 | 4000ℓ | |
| 第4石油類 | 非水溶性 | 6000ℓ |
| 動植物油類 | 水溶性 | 10000ℓ |
指定数量の倍数
指定数量の倍数とは、貯蔵・取り扱う危険物の数量が指定数量を超える時に算出する数字のこと。
指定数量の倍数=危険物の貯蔵量/危険物の指定数量
指定数量の倍数が"1”を超えると消防法の規制を受ける。
2種類以上の危険物を貯蔵する場合は、それぞれの数量をそれぞれの指定数量で割り、その数値の合計が指定数量の倍数となる。
製造所等
【製造所】:危険物を製造する施設
【貯蔵所】:危険物を容器やタンクで貯蔵・取り扱う施設
〇屋内貯蔵所:建物の中で危険物を貯蔵、取扱う施設。
軒高6m未満の平屋建て。床は地盤面以上。床面積は1000㎡以下。危険物の温度は55℃を超えないこと。
〇屋外貯蔵所:建物の外で危険物を貯蔵、取扱う施設。
・架台の高さは6m以下。
・危険物は容器に収納し、容器の積み重ねの高さは3m以下。
<貯蔵可能>
●第2類の硫黄、または引火性固体(引火点は0℃以上)
●第4類の特殊引火物を除いたもの、但し第1石油類の引火点0℃以上のもののみ=ガソリン・アセトンは貯蔵不可!
〇屋内タンク貯蔵所:建物の中のタンクで危険物を貯蔵、取扱う施設。
・タンクの容量は指定数量の40倍以下とする。
・平屋建ての建築物に設けられたタンク専用室に貯蔵する。
・(2つ以上のタンクがある場合)タンクの相互間は0.5m以上とする。
・出入り口の敷居の高さは0.2m以上とする。
・屋根は不燃材料で作り、天井は設けてはいけない。
〇屋外タンク貯蔵所:建物の外のタンクで危険物を貯蔵、取扱う施設。
・危険物がもれた時の流出防止用に防油堤を設ける必要がある。
・防油堤の高さは0.5m以上、面積は80000㎡以下とする。
・防油堤の容量はタンク容量(複数ある場合は最大のもの)の110%以上とする。
〇地下タンク貯蔵所:地面より下のタンクで危険物を貯蔵、取扱う施設。
・地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保ち、タンク周囲に乾燥砂をつめること。
・頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。
・地下貯蔵タンクを2基以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m以上の間隔を保つこと。(2つ以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5m)
・見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
〇簡易貯蔵タンク貯蔵所:簡易タンクで貯蔵、取扱う施設。
・容量は600ℓ以下
〇移動タンク貯蔵所:タンクローリーのこと。
・間仕切りの厚みは3.2mm以上、防波板の厚みは1.6mm以上。
・容量は30000ℓ以下
【取扱所】:危険物の製造や貯蔵以外の木亭で取り扱う施設
〇給油取扱所:ガソリンスタンド
・給油空地を保有する。(間口10m以上、奥行き6m以上 自動車等の出入口、給油用のスペース)
・注油空地を保有する。(灯油、軽油の容器の詰替え、または車両に固定されたタンクに注入するためのスペース)
〇販売取扱所:容器入のまま販売するところ。
★第1種販売取扱所:指定数量15倍以下
★第2種販売取扱所:指定数量15倍を超え40倍以下
〇移送取扱所:パイプライン施設
〇一般取扱所:上記に該当しない施設のこと。
保安距離
メモ
保安距離とは?
製造所の火災、爆発等の災害が付近の住宅、保安対象物に対して、延焼防止及び避難等の目的により、保安対象物からその製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に一定の距離を定めた距離
★保安距離が必要な製造所等
①製造所
②屋内貯蔵所
③屋外貯蔵所
④屋外タンク貯蔵所
⑤一般取扱所
語呂合わせ
せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん
製造所(せいぞうしょ)・屋内(おくない)貯蔵所・屋外(おくがい)貯蔵所・屋外タンク(おくがいたんく)貯蔵所・一般(いっぱん)取扱所
★保安対象物と距離
〇敷地外の住居 →→→ 10メートル以上
〇高圧ガス施設 →→→ 20メートル以上
〇学校、病院、劇場、公会堂等 →→→ 30メートル以上
〇重要文化財等 →→→ 50メートル以上
〇7000V~35000Vの高圧架空電線 →→→ 3メートル以上(水平距離)
〇35000Vを越える高圧架空電線 →→→ 5メートル以上(水平距離)
保有空地
メモ
保有距離とは?
敷地内で、延焼防止、消火活動等のために、危険物施設の周囲に設けられた空地のこと。
★保有空地が必要な製造所等
保安距離が必要なものに簡易タンク貯蔵所、移送取扱所を加えたもの(条件付き)が必要な製造所等になる。
①製造所
②屋内貯蔵所
③屋外タンク貯蔵所
④屋外貯蔵所
⑤一般取扱所
⑥簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの)
⑦移送取扱所(地上設置のもの)
予防規定
メモ
予防規定とは?
製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めた規定のこと。
〇所有者が予防規定を定め、市町村長等が認可する。変更したときも同様である。
〇予防規定が必要な製造所等
・全ての給油取扱所と移送取扱所
・指定数量に応じた製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所
語呂合わせ
せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん +キウイ
製造所(せいぞうしょ)・屋内(おくない)貯蔵所・屋外(おくがい)貯蔵所・屋外タンク(おくがいたんく)貯蔵所・一般(いっぱん)取扱所
+
給油(きゅうゆ)取扱所・移送(いそう)取扱所
定期点検
〇資格者:危険物取扱者(甲乙丙)、危険物施設保安員、危険物取扱者(甲乙丙)の立ち合いがあれば無資格者でOK
〇回数:1年に1回
〇記録:定期点検を実施し、点検記録を作成し、3年間保存 ※点検結果を市町村長等に報告する義務はない。
〇点検記録内容:
①製造所等の名称
②点検の方法と結果
③点検年月日
④点検を行った危険物取扱者、危険物施設保安員、点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
〇定期点検が必要な製造所等:
・指定数量の倍数に関係なく:地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所、地下タンクを有する製造所・給油取扱所・一般取扱所
・指定数量による:製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所
※点検不要:屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所
〇漏れの点検:移動貯蔵タンクは5年以内に1回以上、点検記録は10年間保存。
危険物の運搬
〇混載:指定数量の倍数が0.1以上の危険物の混載ができる組み合わせは、2つの類の数字を足して7になるものと、第2類と第4類、第4類と第5類
消火設備
〇第1種消火設備:屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
〇第2種消火設備:スプリンクラー設備
〇第3種消火設備:水蒸気、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲンガス、粉末消火設備
〇第4種消火設備:大型消火器
→保護対象物から歩行距離が30m以下に設置
〇第5種消火設備:小型消火器、乾燥砂
→保護対象物から歩行距離が20m以下に設置
製造所等の義務一覧


下の講義内容も是非ご覧下さい!!
関連
危険物乙4 の講義内容(物理・化学編)
【スキルアップ-危険物乙4】『試験に出るポイントのまとめ』_物理学・化学編
関連
危険物乙4 講義内容(性質・消火編)