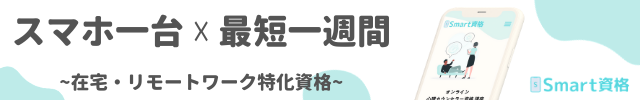第29回目の対策講座の今回は、
【消火設備・警報設備の基準】(分類:法令#12)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.灯油の消火に適応する消火器として誤っているものはどれか
1. 泡を放射する消火器
2. 二酸化炭素を放射する消火器
3. 霧状の強化液を放射する消火器
4. 粉末を放射する消火器
5. 霧状の水を放射する消火器
目次
消火設備の種類
消火設備は、第1種から第5種に区分されている。
第1消火設備:屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2消火設備:スプリンクラー設備
第3消火設備:水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4消火設備:大型消火器
第5消火設備:小型消火器、簡易消火用具(バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩)
製造所等に設置する消火設備
製造所等に設置する消火設備は、規模・形態・危険物の種類、量等に応じて3つのパターンに分けられる。
①著しく消火困難な製造所等 ⇨⇨⇨ 第1種+第2種又は第3種消火設備+4種及び5種消火設備
②消火困難な製造所等 ⇨⇨⇨ 第4種+第5種消火設備
③その他の製造所等 ⇨⇨⇨ 第5種消火設備
規模・形態・危険物の種類、量等に関係なく、消火設備の設置が必要な製造所等、または設備もある。
●移動タンク貯蔵所:自動車用消化器のうち、粉末消火器またはその他の消火器を2個以上設置する。
●地下タンク貯蔵所:第5種消火設備を2個以上設置する。
●電気設備:電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設置する。
所要単位
建築物や危険物の量など、消火設備の設置対象に必要な消火設備の能力を定める際に用いる基準単位を【所要単位】という。
| 建築物・危険物 | 1 所要単位当たりの数値 | |
| 製造所・取扱所 | 耐火構造 | 述べ面積 100 m² |
| 不燃材料 | 述べ面積 50 m² | |
| 貯蔵所 | 耐火構造 | 述べ面積 150 m² |
| 不燃材料 | 述べ面積 75 m² | |
| 屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし,水平最大面積を建坪とみなして算定。 | |
| 危険物の数量 | 指定数量の10 倍 | |
能力単位
所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準単位を【能力単位】という。
製造所等では、所要単位に応じた能力単位を有する消火設備を設けなければならない。
消火設備の設置基準
①第1種消火設備
屋内消火栓設備:各階毎、その階の各部分から1つのホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設置する。
屋外消火栓設備:防護対象物の各部分から1つのホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設置する。
②第2種消火設備
スプリンクラー設備:防護対象物の各部分から1つのスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下となるように設置する。
③第3消火設備
水蒸気消火設備:放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
水噴霧消火設備: 〃
泡消火設備: 〃
不活性ガス消火設備: 〃
ハロゲン化物消火設備: 〃
粉末消火設備: 〃
④第4消火設備
大型消火器:防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設置する。ただし、第1種、第2種、第3種の消火設備と併置する場合はこの限りではない。
⑤第5消火設備
小型消火器、簡易消火用具:地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所:有効に消火できるように設置する。
その他の製造所等は、防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設置する。ただし、第1種、第2種、第3種、第4種の消火設備と併置する場合はこの限りではない。
警報設備
火災、危険物流出などの事故を迅速に従業員等に知らせるため,指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には,【警報設備】を設置しなければならない。警報設備には,次の5種類がある。
①自動火災報知設備
②消防機関に報知できる電話
③非常ベル装置
④拡声装置
⑤警鐘

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
関連
危険物乙4 前回の講義内容(第29回)
【スキルアップ-危険物乙4】『危険物の性質』_第29回
関連
危険物乙4 次回の講義内容(第31回)