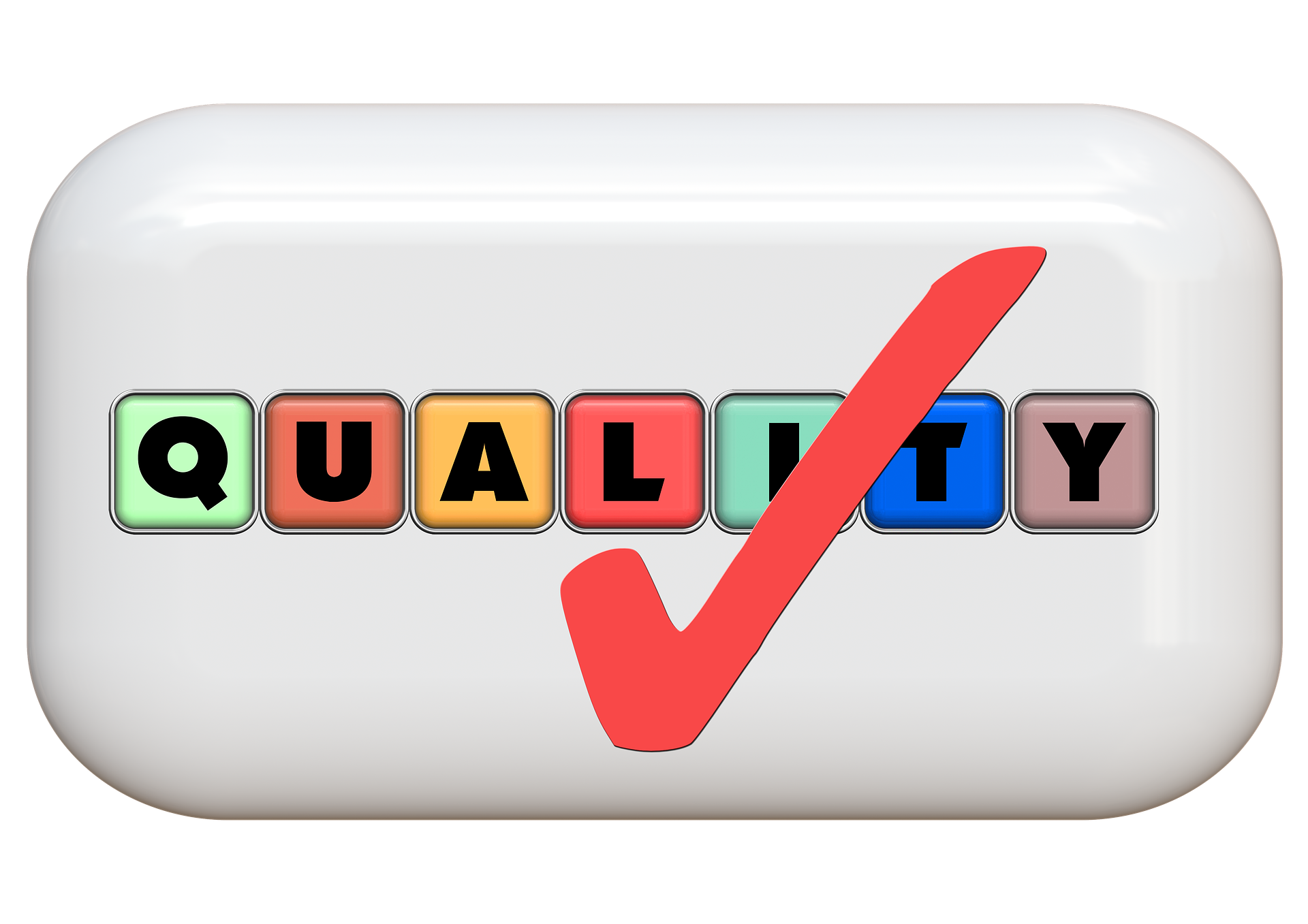第24回目の対策講座(手法編#16)の今回は、
【新QC7つ道具 #3-系統図法】
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。

QC=Quality Controlの略で品質管理の意味。また職場内で自発的に集まった少人数の集団が、製品・サービスの品質管理や改善、不具合品の低減、安全対策に取り組む(QC活動)ことをQC活動という。
↓QC(品質管理)検定の概要に関しては、下記リンクをご覧ください↓ 目次 サブローこんにちは。サブローです。 本日はQC検定(品質管理検定)について説明をしていきますので、よろしくお願いします。 目次 QC検定とは? QCとは【Quality Control】の略であり、本 ... 続きを見る

【QC検定対策】 QC(品質管理)検定とは?(2020年度版)
↓QC(品質管理)検定講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓ サブローQC(品質管理)検定に関する説明が増やして行く予定なのでリンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 モグゾー対象級を記載していますが、あく ... 続きを見る

【QC検定2級対策】講座-目次(INDEX)
新QC7つ道具
新QC七つ道具とは、QC7つ道具が「数値データ」を分析する手法に対し、主として「言語データ」をわかりやすく図に整理することによって、混沌としている問題の解決を図っていく下記7つの手法です。これらは、製造現場を中心に展開されていたQCサークル活動が、TQCへと進展し、設計開発部門、営業部門などの間接部門へ活動範囲が広がるのにつれて、問題の解決手法や創造、発想手法を組み入れ、問接部門で活用できるQC手法として、開発されたものです。
①親和図
②連関図法
③系統図法
④マトリックス図法
⑤アローダイアグラム法
⑥PDPC法
⑦マトリックス・データ解析法
今回の講座では、その中の【系統図法】を説明していきます。
【系統図法】
◎:内容を実務で運用できるレベル
○ :内容を知識として理解しているレベル
△:言葉を知っている程度のレベル
×:出題範囲ではない項目
「目的」に対する「手段」を決め、次にその「手段」を「目的」にして、「手段」を決めます。順番に行っていきます。
「系統図法」のメリットを系統的にツリー状にすることで論理展開しやすく、抜け、漏れが少なくなります。また目的と手段の関係が明確になり、関係者、第3者への説明が容易になります。メンバーの意思の統一が図りやすくなります。
【系統図法の種類】
「系統図法」は、主に次の2つの種類があります。
<構成要素展開型>
問題の要因を掘り下げる系統図法。要素を分解して掘り下げていきます。
<方策展開型>
解決策を具体化する系統図法。方策を展開していきます。
【系統図法の作り方】
1.課題の設定
⇒「連関図法」で取りあげたテーマ、あるいは解決したい問題を「〜を〜するには」という表現にし、言語カードに記入します。
具体的に表現することが大切です。ここで決めた内容が「目的」または達成したい「目標」となります。
2.制約条件の設定
⇒目的・目標を達成するための方策を展開するにあたって、制約条件が必要な場合には「制約事項」を決めておきます。(XXXの機材は使用しないなど)
3.方策の抽出
⇒目的を達成する「一次手段」を全員でディスカッションします。2、3枚抽出して、ラベルに記載していきます。.模造紙を広げ、目的を左端中央に置きます。
「一次手段」をその右側に並べ、線でつなぎます。また制約条件がある場合は、目的の下に制約条件を記載します。
5.方策の掘り下げ
⇒「一次手段」を目的として、これを果たす手段を「〜を〜する」とラベルに記載していきます。以降も同じようにして、「二次手段」を目的として「三次手段」をメンバー全員でよく話し合いながら抽出しラベルに記入して、模造紙に配置していきます。(大体三次か四次手段あたりまで展開します。)
7.チェック
⇒「三次手段」まで展開できたら、再度、「目的」から「一次」、「二次」、「三次」へと手段を全員で見直します。次に三次手段から逆に目的を確認して、必要に応じて、新たな手段を発想してラベルを整理し追加します。完成した系統図の手段に対し、重要性、経済性、実現性、効果などの面から優先順位を決めます。


下の講義内容も是非ご覧下さい!!
関連
QC検定対策 前回の講義内容(第23回)
『連関図法』-【QC検定の対策講座】#23
関連
QC検定対策 次回の講義内容(第26回)